第1回 Bioconductor Carpentries 日本語 ワークショップ
大阪大学 微生物病研究所 2025-08-05 ~ 06
https://bioconductor-translations.github.io/2025-08-05-osaka-slides/
アウトライン
- スタッフの自己紹介、JSBiの紹介等
- Bioconductor と The Carpentries の紹介
- ワークショップの流れ
- アイスブレーカー
スタッフの自己紹介
西田 孝三(インストラクター)
理化学研究所 生命機能科学研究センター 技師
趣味:オープンソース・オープンサイエンスコミュニティに貢献すること
プロジェクト: Bioconductor パッケージ作成・コミュニティ管理

後藤 直久(ヘルパー)
大阪大学 微生物病研究所 講師
研究: ゲノムレベルの遺伝情報解析
プロジェクト: BioRuby

行動規範
どなたでも気兼ねなくワークショップに参加できるように、行動規範があります。
行動規範に反する行為があった場合は、インシデントレポートフォームで報告することができます。
JSBiについて

このワークショップは 日本バイオインフォマティクス学会 の 公募研究会・地域部会として採択され、ご協力をいただいています。
非会員の方はぜひ入会をご検討ください。
準備
Bioconductor の紹介
Bioconductorとは?
- バイオインフォマティクスのためのRパッケージの集合体(多くのRパッケージがBioconductorに登録されており、研究目的に応じたツールが多数揃っている)
- 再現可能な解析(コードとドキュメントがセットで提供されるため、解析の再現性が高い)
- 専門性の高いデータ構造(
SummarizedExperimentやGRangesなど、バイオデータ特有の構造に適したクラス設計がされている)
The Carpentries の紹介
問題
研究者は近年、コードを使うことが必要不可欠になっています。
多くの研究者は独学でコードを学びます。
しかし、効率があまり良くありません。
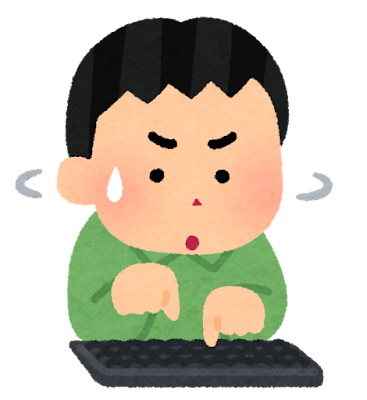
The Carpentries の解決法
研究者がコミュニティを作り、互いに教え合います。
2日間にわたるワークショップで、2〜3つのレッスンを学びます。

ワークショップ
誰でも参加可能
無料または少額で提供
ワークショップの指導には資格が必要です。
改善のためのフィードバックを重視します。
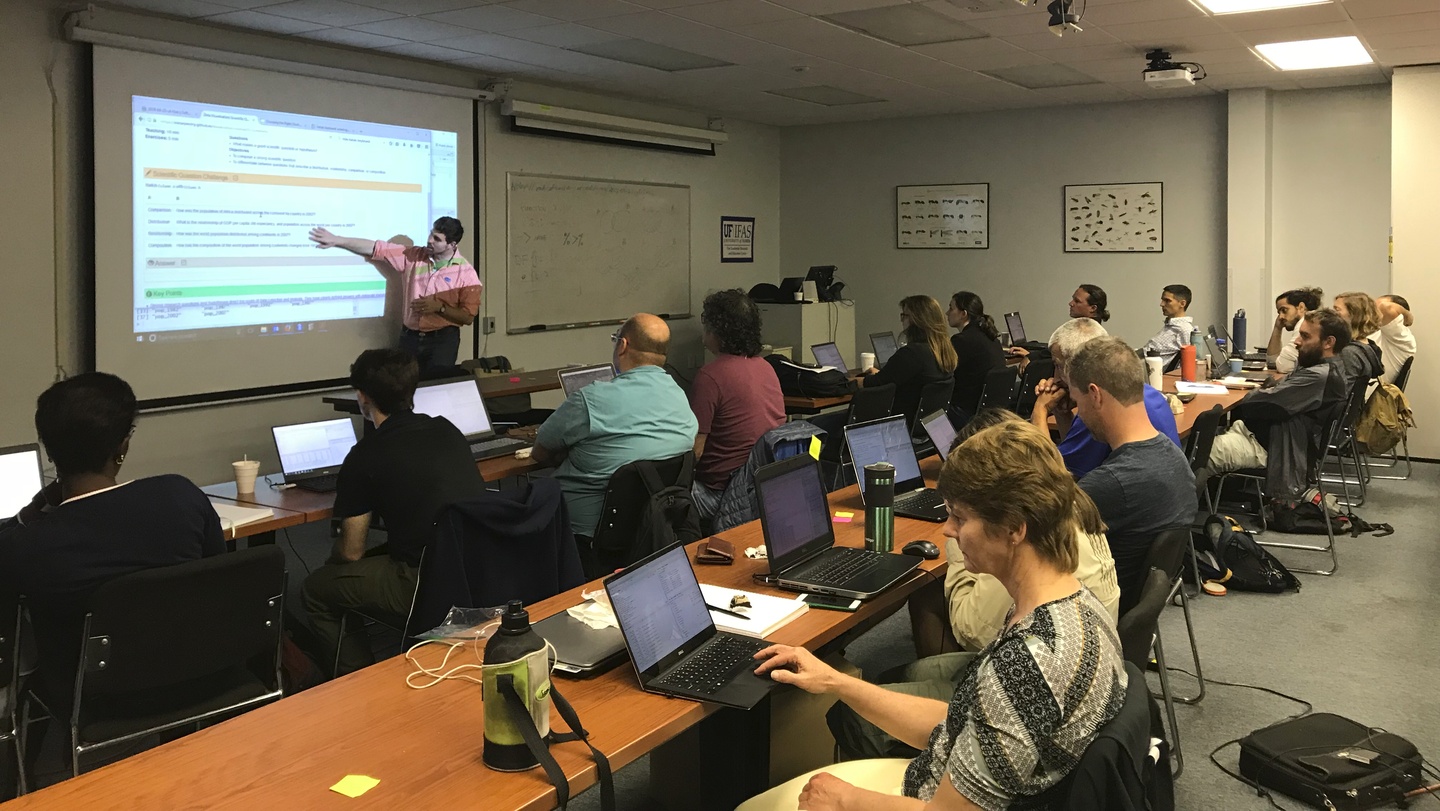
世界各国で実施
日本ではまだ始まったばかり
- 今回が第1回目の対面 Bioconductor Carpentries 日本語ワークショップです。
- 英語教材の翻訳活動も行っています。(翻訳に関するウェブサイトは現在構築中。詳細は後述のSlackでお声がけいただければと…)
参加者大募集中!
Slack:
- https://slack-invite.carpentries.org/ から Slack に参加し、
#local-japanチャンネルに入ってください。
- https://slack-invite.carpentries.org/ から Slack に参加し、
GitHub:
ワークショップの流れ
内容
上記のリンクからレッスンの内容にアクセスできます
(PLaMo翻訳による翻訳が含まれています)
ワークショップの流れ
- ライブコーディング
ライブコーディングとは?
インストラクターが入力するコードを、同時に自分のパソコンで入力します。
コードを理解することを最優先してください
(メモを取るよりも)。

ライブコーディングとは?
インストラクターは参加者の理解を確認します
(例:「〜ができましたか?」)理解できている場合は、Zoom ウェビナーのリアクションでポジティブなリアクションを行ってください。
困ったことがある場合は、 Zoom ウェビナーのリアクションでネガティブなリアクションを行ってください。
- インストラクター/ヘルパーが質問に応じます。
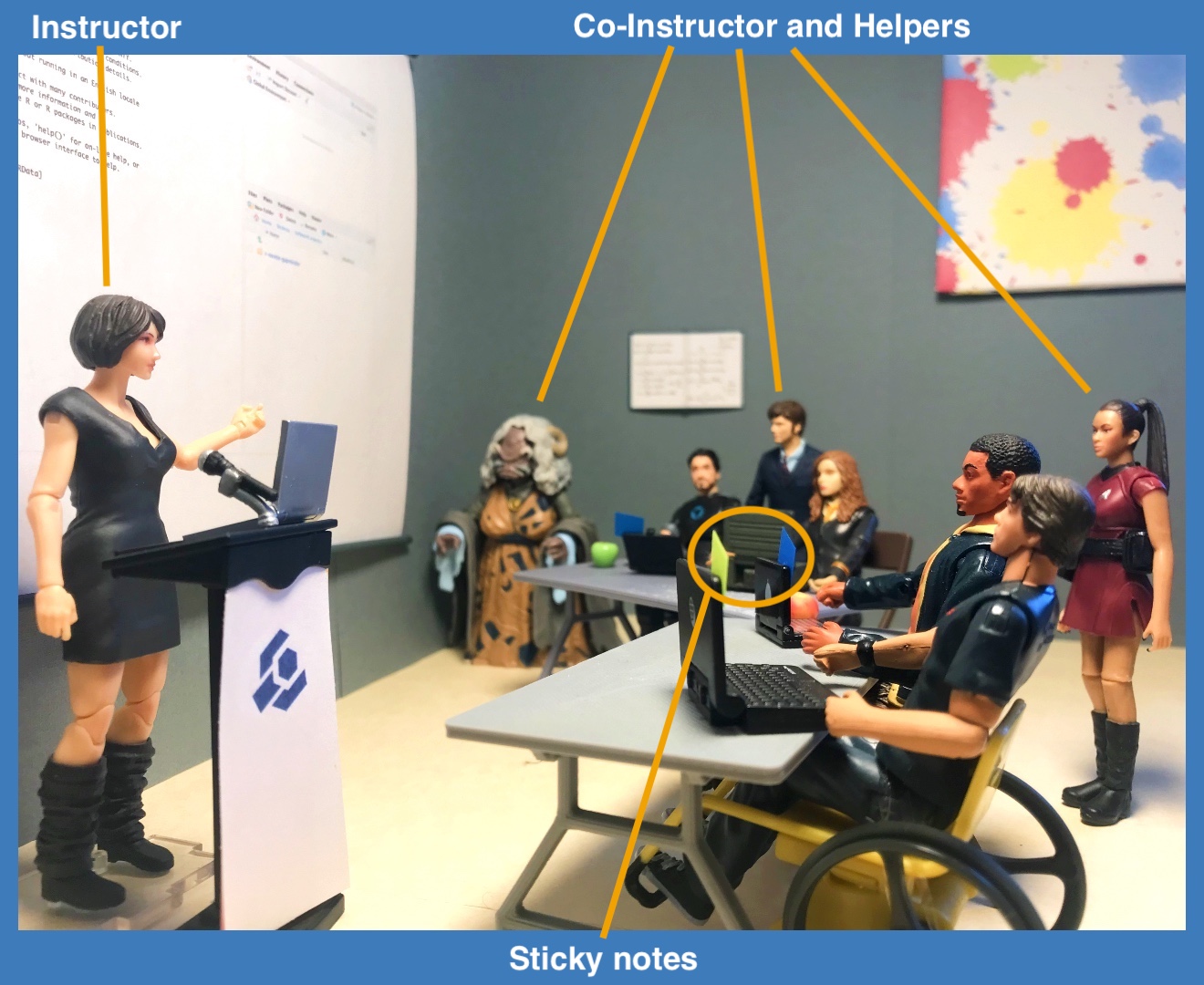
インストラクターが聞かなくても、何か問題があった時は声をかけてください。
コラボレイティブ・ノート
Google Docsにコードを貼っておきます。
- インストラクターが進みすぎてコードが見えなくなった場合は、Google Docsのメモを参照してください。
- 参加者も自由に書き込んでください。
フィードバックの種類
感想
集合写真
「公開しても大丈夫」という方は、ぜひご協力ください。
後ろから撮影した集合写真を公開する場合があります。もし公開を希望されない場合は、お知らせください。
アイスブレーカー
初対面の人同士が集まる場や、会議やセミナーなど、緊張した雰囲気の中で、参加者同士がリラックスしてコミュニケーションを取りやすくするために行う、場を和ませる活動のこと
現地限定になりますが、簡単に参加者にも自己紹介お願いできればと。